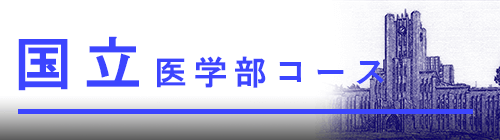入試英語の長文化
最近の大学入試の英語問題を見て驚くのは、まずその英文の長さである。膨大な量である。昔も上智大学や慶応大学など一部の私大ではかなり長い英文が出題されていたが、近年は国立大学も長くなっている。東大でさえ、30年前の問題と比べると、3、4倍の長文を処理しなければならない状況である。他方、京都大学など昔からの長さを保持している大学も一部は残っている。
なぜこうも英文の量が増えたのであろうか。そして英文は長い必要があるのだろうか。畢竟、大学入試の英語は受験生の何を見ようとしているのであろうか。
受験英語は長い間批判の的であった。中学から大学卒業まで日本の学生は10年も英語をやっているのに英会話一つできないというのがその論調の中心である。時代もますますグローバル化して、国際的な交流が深まり、外国人との丁々発止のやり取りが必要になってきている。それを受けて大学入試にリスニングが導入され、筆記の入試問題に英会話が登場するようになった。さて、こういう現実をどう理解すればよいのだろうか。
時代の流れと大学入試制度改革
大学入試のありかたは、時代状況が変化すれば変わっていくのは当然であるが、しかし、その教育の変革を行うとき、何を変えて何を変えるべきでないかがチグハグになることが多々あるのである。かつての「ゆとり教育」がそうであった。「詰め込み教育」が批判されて、では改革をとばかりにただ教える量を減らすという表面的な改革に終わり、結局それが裏目に出てまた元に戻るという杜撰さである。こうした悲劇(教育を受ける側にとっては大変な悲劇である)が起こるのは、教育とは何かという本質的な視点がないからであろう。だから場当たり的な改革になるのである。
英語教育が必要だというとき、国民のどの範囲にどのレベルの英語が必要かという根本的な視点がない。大学生に英語が必要だというときに、中学生の英語と何が違うのかの視点がないのである。なぜなら、大学の英会話の入試問題を見てみるとよい。アメリカの中学生レベルの会話である。それに正答することを求める大学は受験生に何を求めているのであろうか。現在の大学入試の英語は海外体験者(いわゆる帰国子女)に圧倒的に有利にできている。アメリカの高校生が解いたら満点をとるレベルの内容なのである。そういうレベルの問題で大学に必要などういう学力を求めているのであろうか。
結局大学とは何かという根本的な確認が文部科学省にないために、商業主義に任せるままに大学を粗製乱造し、そのレベルにあった入試問題を作るという悪循環を生みだしてしまっている。
大学の知性と英会話
さらに問題なのは、東大はじめ本来の大学の使命を持っている大学も、受験生にリスニングが課されることになった。東大は120点中4分の1の30点の配点となっている。リスニング力が大学レベルの学力とは何の関係もないにもかかわらずである。なぜなら、アメリカの高校生は誰でも東大のリスニングをクリアするであろうからである。外国語だから意味があるのだという論理も成り立たない。学力に関わらず、海外経験があるというだけで有利だからである。外国語のリスニング力は本来大学生に求める学力とは何のかかわりもないのである。先年ノーベル物理学賞を受賞した名古屋大学の教授が英語が不得手で、授賞式のスピーチを日本語で行った。それで何の問題もない。物理学の優秀さと英語力とは何に関係もないのである。
後期試験の失敗
現在東大の後期試験は理科Ⅲ類では実施せず、他も理科Ⅲ類を除くすべてを合わせて100人と文科省への付き合い程度に減っているが、かつては各科類で一定数を後期試験でとっていた。しかし、後期試験は文系の場合センター試験が数学は数学①(数1と数A)とだけでよく、東大の二次試験では膨大な英文と日本文を読ませての小論文試験で、帰国子女あるいは留学経験者に有利であった。実際私も「えっ!」という生徒が文科Ⅰ類に合格したのを経験している。もちろん本人には「おめでとう!」と伝えたが、これでいいのだろうかと疑問に思ったものである。何しろ、基本的な学力は東大に程遠いのであるが、センター試験の数学①と小論文対策だけを一生懸命準備するわけである。あとは帰国子女の有利性をいかんなく発揮して東大合格である。この時代、女子高校生の中にこの制度を利用して最初から東大後期狙いで受験準備した生徒が多数いたそうである。しかし、案の定大学側はそうやって入れた学生の学力の低さに呆然としたのであろう。何年か後に一気に後期試験を縮小したのである。しかし、そうした事態を予測できない文科省の役人たちや東大の先生方も困ったものである。それもこれも大学とは何か、国にとって大学生とは何かという本質論を持っていないからなのだろうと思う。
国は大学に膨大な予算をつぎ込んでいる。国立大学に年間1兆円の運営交付金が配られている。大学生を育てることに多大な国民の税金をつぎ込んでいるのである。それはなぜであるか。言うまでもなく、優秀な人材を育て、国家社会のために活躍してもらいたいからである。しかも、それは社会の枢要な部分で活躍してもらうということであるから、高度な学問と豊かな教養と深い洞察力を持つ人材であるべきである。であるから、東京大学や京都大学の問題はそのレベルが可能な人材を見分けるような入試問題が伝統的に作られてきたのである。
大学入試で英語を学ぶ意義
外国語を学ぶ意義も、外国語を通して学問をすることに意味があるのであり、その英文を日本語に訳したとしても本当の読解力がなければ文意をつかめないような高度な内容の問題であった。しかし、近年は問題文が長くなった分、内容は薄くならざるを得ず、膨大な情報をいかに速く処理できるかを競うような傾向に変わりつつある。大学生の質が軽くなっていくのは当然であろう。
東大の質が軽くなれば、やがて彼らが官僚となって国家の命運を握っていくのであるから、国民の生活に関わってくることに恐怖を覚えてほしいものである。東大の入試問題はリスニング問題を作るよりも、受験生が国民の福祉を考えた国造りにいかなる問題意識と志を持っているかを見て取るような問題をこそ作るべきなのである。
かつての大学受験の英語はイギリスの知識人、教養人が書いた英文が素材であった。それは、やがて日本の最上の知性を形成することになる大学進学準備者(=大学受験生)をイギリスという国の最上の知性と原文で交流させる意味があったのである。したがってその話題は、科学とは何か、学問とは何か、教養とは何か、教養人とは何か、民主主義とは何か、文化とは何か、人間とは何か、社会とは何か・・・といった内容であったのである。外国語を大学で学ぶということは、学ぶに足る外国の、学ぶに足る知性と、原文を通して交流するということが必要だからであった。それは英語を学ぶというよりも、英語で学ぶという意味があったのだが、しかし、言語は思想と直接に結びついているのであるから、その過程で、当然に英語そのものを学ぶことになり、そしてそれは単なる英会話のレベルではなく、思想というレベルの内容を扱っているだけに、そのレベルで英語そのものの学びが要求され、そこから必然的に自国の言語そのものに対する自覚と意識的学びが要求されるという構造を外国語学習は持ったのである。
英語の世界と英会話は異なる
それがいつのまにか言語の持つ表面的な側面つまりコミュニケーションの手段・道具にすぎないという側面を強調する流れが出てきた。それは先ほど述べた日本の大学生が英会話ができないという事実やグローバル化の時代の流れで国際的なコミュニケーションが必要であるという現実からの要請が背景にある。時代の変化に応じて制度を変えていくということは当然必要なことである。しかし、問題となる対象をしっかり把握せずに変革を試みれば変革が改正ではなく改悪になることを覚悟しなければならない。
外国語学習で大事なことは、コミュニケーションの道具としての外国語と大学で扱う外国語とは表面上は同じ外国語であっても本質的に別物なのだという理解である。アメリカのスーパーの買い物で使う英語と大学の英語は別物なのだという理解が必要なのである(使う単語が違うとかそういう話ではないことは今までの話で理解していただけると期待したい)。大学生にもコミュニケーションの道具としての英語を求めるのであれば、それは先程も述べたように、大学入試問題(何しろこれは大学生のレベルでなければ答えられない問題でなければ意味がない)でそれを問うのではなく、それ以前の受験資格試験にするか、入学後に一定の基準を課すかすればよいことである。いずれにしても、コミュニケーションの道具としての英語力は大学入試とは別問題として考えなければならないということである。たとえば高度成長期、これからはモータリゼーション社会(自動車社会)であるからと言って、入社試験で入社希望者に自動車を運転させてみた会社があったであろうか。大学入試で英会話の問題を出すというのは、入社試験で車の運転をさせてみるというに等しいのである。そろそろそうしたばかげた発想はやめてほしいものである。そうでないと日本の大学生のレベルはますます下がっていくであろうからである。
そして、日本語で高度な文化を世界に発信して、かつて日本がドイツ語を英語で学んだように、諸外国の学生がこぞって日本語を学ぼうとする時代を切り開こうというくらいの志を日本の役人も大学関係者も大学生も持ってもらいたいものである。
羅針盤の記事一覧はこちら。